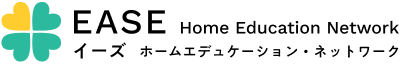Sさん
わが家は息子が2人おります。息子達はそれぞれのタイミングで不登校の時期、ひきこもりの時期がありました。夫が不登校関連の情報収集をする中でホームエデュケーションに出会いました。長男が高校2年生、次男が中学2年生の春に家族でイーズに入会。主に交流活動に参加させていただいております。
長男はスペース活動にも参加。毎月違った場所へ出かけ、スポーツ観戦、芸術鑑賞、サイクリングなど貴重な経験をさせていただいております。他人との関わり方の練習や初めての場所への対応など、長男の苦手意識の緩和に役立っていると思います。
Aさん
息子が不登校になった時は、息子のすべてが止まってしまったような感じでした。母親として言い表せない程のショック、不安、孤独感でいっぱいでした。
毎日無気力に過ごす息子をみて、私の中で焦りが出てきました。学校で勉強ができないなら自分で教えるしかないと自宅学習を試みたり、息子に対してできることを手あたり次第やってみたりしました。しかし、どれも上手くいきませんでした。
ある日「ホームエデュケーション」という言葉を知りました。ホームエデュケーションに出会わなかったら、負のサイクルから抜け出せなかったかもしれません。ホームエデュケーションとの出会いから、親子の関係性や思考が変わっていきました。
ホームエデュケーションをすすめていく初期段階で気付かされたことがありました。「不登校=子供に問題がある」とか「この子をなんとかしなきゃ」という思考にこそ問題ということでした。まず息子でなく、親である自分が変わることが必要でした。変わらない自分が息子を変えることは、不可能でした。いかに親子の良い関係性をつくる土台づくりが大事かを教えてられました。
不登校に関する書物も読みました。病院のカウンセラーにも会いました。いただいた言葉やアドバイスは一次的な慰めにはなりましたが、根本的な解決には繋がらなかったと思います。そのような状況下で、イーズのスタッフは本気で関わって下さり、的確なアドバイスを送り続けてくださいました。その結果、徐々に息子も自分の気持ちが話せるようになり親子の絆が深くなっていくのを感じました。今では息子と色んなことを本音で話し合っています。息子から助けられることも増えました。
ホームエデュケーションをやってみてわかったことは、ホームエデュケーションは、例えるならばオーダーメイドの服と似ているということです。その子に合った育ちです。ただ勘違いしてはいけないことは、ホームエデュケーションは子どもが好きなものだけを与えたらいいというものではないということです。大事なこととは、子どもが自立し、人生に喜びを見つけながら生きぬいていくために必要な学びを探求し、築き上げていくことだと理解しています。
息子は今19歳です。就職後一人暮らしを始め、一年が過ぎようとしています。就職したらそれがゴールではないことを息子もよく理解しており、ときどき直接スタッフに連絡をとって職場のことなど相談しています。息子は驚くほど独立し、日々充実した生活を送っています。
私達家族は、イーズをホームエデュケーションのプロだと思っています。今16歳の娘の進学についてもサポートしていただいています。今までたくさんお世話になった分、少しでもお返しできることがあればという気持ちでこの体験談に投稿させていただきました。これからもイーズのホームエデュケーションに賛同し、活動を応援し続けたいと思っています。
もし、ひきこもっているお子さんがいらっしゃる保護者の方が、ホームエデュケーションの素晴らしさを少しでも感じていただけたら幸いです。
美樹さん
うちには息子と娘がいます。息子は中2の5月から、娘は小学4年6月から不登校でした。
息子は引きこもり型で、毎日仕事のようにゲームをしていました。たっぷりゲームをしている引きこもり状態を観察していたら、「普通の生活がしたい」となり、提携の通信高校へ進んで彼の社会復帰プログラムがスタートしました。毎日少しずつ課題や、ちょっと苦手だけどしたいこと等をこなす日々が続きました。専門学校を経て国家試験を受け、今は放射線技師になり、病院勤めをしています。念願の社会復帰を果たしましたが道は半ばと感じています。
娘はフリースクールを使った後、英会話塾や予備校を利用して高認資格を取得、今は外国語の専門学校から大学編入に向けて勉強しています。
学校を利用してもしなくても、大人になっても、誰でも「自分を生きていく」ことは変わらないことだと私は考えます。「自分」ってどんな人なのだろう?自分から見た自分、他者にとっての自分。自分がどうしてもだめなこと・もの・環境はどんなものだろう?逆に好きだなあとかちょっと得意かもしれないのはどんなものだろう?自分(客観的な自分も含め)を何度も見つめて、家族という仲間で一緒に考えながら、どんどん自分がなりたい自分になっていこうとそれぞれが試行錯誤しながら暮らしています。実は学校を使わなかったことでこの環境を作り易かったのでは?と考えています。
息子は最近、仕事でのしくじりや人間関係から自らの頑なさに気づき、自分の本質を押さえ込まずに生きていく実験を始めました。娘は同級生や先生との付き合いから、力を入れない関係の結び方を習得、自分への厳しさも少しずつ緩めている様子です。今後もそれぞれ、自分を開いたり緩めたりして、さらに「自分が満足できる自分」になっていってくれるといいなと思います。
Mさん
わが家では、現在17才の娘と14才の息子がイーズに参加させていただきながらホームエデュケーションで育っています。
わが家では親がスタッフからコンサルテーションを受けており、1~2か月に一回、子ども達の近状報告をさせていただき、アドバイスや指摘をうけ、日々のホームエデュケーションに活用させていただきながら過ごしています。
月に一度、リアル交流会を有志で開催しています。リラックスした中で一緒にSwitchで遊んだり、ボードゲームやカードゲームで盛り上がったり、おしゃべりしたりと、なかなかリアルで集まって遊べる機会は我が家では少ないので、貴重な時間をいただいています。保護者同士でも、楽しくおしゃべりしたり、子ども若者と一緒にカードゲームで盛り上がったりと私にとっても、楽しく貴重な時間です。
年に一度の全国お泊まり会(合宿)では、ホームエデュケーション仲間が集まり、最初は緊張していた子ども達も、今では参加するのが楽しみのようで、私もなかなか日頃お会いできない保護者の方とお会いでき、おしゃべり出来るのが楽しみです。
日常ではイーズの交流サイトslackを使い、イーズの保護者の方と繋がれているので、何かちょっと相談したり、日常の小さな事を共有できたりと、私は仲間と繋がれている安心があります。子ども達も子どもslackにそれぞれ入っていて、描いた絵を投稿したり、ちょっとしたことを投稿したり、他の方の投稿を見たりと活用させていただいているようです。
これからもイーズを活用させていただきながら、子ども達の道がどのように広がっていくのかがとても楽しみです!
Hさん
うちの子供が不登校になったのは、小学校の低学年の時です。当時は不安がとても強くフリースクールなどはもちろん外出もしたがらず、ずっと家で引きこもっているような状態でした。
そんな時、支えとなったのが同じように家で過ごしている子どもの保護者の皆さんでした。それぞれのホームエデュケーションを日々試行錯誤しながら前向きに実践されており、またそんな環境で素敵に育ったお子さん達を目の当たりにして、家で成長するのも悪くないな、むしろうちの子に合ってるなと、私自身の考えが変わりました。そんな私の変化とともに子供もだんだん元気を取り戻していきました。
そんな経験から、イーズでも保護者同士気軽に集まれる場所がほしいと思い、「親カフェ」を始めました。いまは、従来の在宅不登校対応の常識から何歩も進んだホームエデュケーションをされている先輩保護者の皆さんのお話を聞けるのがとても楽しみです。また、リアルに会って皆さんの暖かい空気に触れる事で、うちも頑張ろう!と力が湧いてきます。
まだまだ、私自身のホームエデュケーションに自信がなくなる時もありますが、イーズでの保護者の皆さんとの交流やスタッフの方々のアドバイスに元気をいただいて、我が子とのかけがえのない日々を過ごしています。
Wさん
「もう、俺はあんな風に制服着て、放課後みんなで遊びに行ったり出来ないんだね・・。」
ホームエデュケーションを知らなかった頃、下校中の高校生を見て息子がつぶやいた言葉です。寂しそうな息子を見て、親として間違った選択をしたのだろうか・・と、胸が締め付けられました。
中1から不登校になり、中2から所属したフリースクールも全く通うことなくどんどんふさぎ込んでいく息子。何か好きなことを経験して欲しいと思い、色々提案するも、どれもいまいちで、人と会うどころか外に一歩も出られず。
前髪で顔を隠し、食事以外は部屋に籠もり、ゲームと動画で過ごす日々でした。「楽しくて一日中ゲームやってるわけじゃないからね」と言ったり、先の不安を訴える息子を見て、私はあらゆるところに出向き『どうしたらひきこもりから脱出できるのか』を相談し、考えていました。でも、この私の考えを変えるように言われたのはイーズが初めてでした。
イーズでは、息子をよく知り、息子に合う育ちを考え、自由に実践できる楽しさを教えてもらいました。昔、よく言われた「お母さんは、本当に頑張っています」「皆で一緒に考えていきましょう」という、優しいけれど気休めでしかない言葉をスタッフは言いませんでした。家庭での過ごし方の提案や、上手くいかない時の私の考え方の指摘などを頂き、誤った方向へ時間と労力を使うことがなくなりました。
現在、息子は、イーズの宿泊イベントに自ら「参加したい」と言うようになり、よく笑い、よくしゃべり、将来の話も前向きにするようになりました。保護者の方が企画してくださる交流の場にも親子で参加しています。少しずつ成長している息子ですが、まだまだ先は長く『ひきこもり経験者は、またひきこもりやすい』という言葉を心に留めて、今後もスタッフにアドバイスを頂きながらホームエデュケーションを楽しんでいきたいと思います。