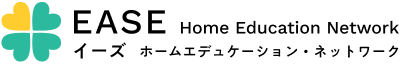Q1 子どもが参加せず、親だけでもいいですか?
A はい。保護者様のみのご利用も多いのでご安心ください。保護者が安心して暮らしていけることは、子どもにとっても大切なことです。
Q2 地方在住でも利用できますか?
A はい。オンライン対応のコンテンツもいろいろあり、全国どこからでもご利用いただけます。
Q3 きょうだい2人の場合、会費は2人分ですか?
A いいえ。会費は1世帯ごとになっております。お子さんの年齢が6歳以上26歳未満で不登校や不登校経験者であれば、ごきょうだい何人でも月額8800円です。
Q4 不登校や引きこもりだと社会性が育たないのでは?
A 当会の会員は、社会性を大事に考えて入会されています。
「就学・就労させるべきか否か」という議論は、現時点で就学・就労しそうもない人にとっては意味がありません。「就学・就労しないと社会性が・・・」と言ったところでそうしなければ意味をなさないし、無理に就学・就労させてしまうと、余計に学校や社会を拒絶するようになるかもしれません。
「教育支援センターやフリースクールに行くべきでは」という考えも、学校に行こうとしない人、行くことを拒絶している人の前では意味を持ちません。
そもそも、在宅不登校になったり、引きこもり状態になった人には、対人関係において自信を失い、過剰な不安を覚えるようになった人が多いのです。問題の本質は、この「対人関係への過剰な不安」であって、「どこに通うか」ではありません。過剰な不安のままで何らかの通所施設に通うことは、かえってその不安を強めてしまうことになりかねません。
もし、その人が、対人関係への過剰な不安によって在宅不登校や引きこもりになったとしたら、「在宅からスタートできる」ということは、選択しやすいことです。イーズで最も求められている活動は「交流」です。人と出会いたい、最初は無理でもいつかはつながりたい、そういった思いを持っているが、なかなか踏み出せないでいた、そのような人のニーズに応えたいと思っています。
また、対人関係への過剰な不安がない人には、「近くにフリースクールがない」「不登校に偏見のない人と交流したい」「ホームスクーリングを実践しながら子ども時代を有意義なものにしたい。そのためにも仲間と出会いたい」といったニーズで選ばれており、やはり社会性を大事に考えて入会する人が多いと思います。
「就学・就労させるべきか否か」という議論は、現時点で就学・就労しそうもない人にとっては意味がありません。「就学・就労しないと社会性が・・・」と言ったところでそうしなければ意味をなさないし、無理に就学・就労させてしまうと、余計に学校や社会を拒絶するようになるかもしれません。
「教育支援センターやフリースクールに行くべきでは」という考えも、学校に行こうとしない人、行くことを拒絶している人の前では意味を持ちません。
そもそも、在宅不登校になったり、引きこもり状態になった人には、対人関係において自信を失い、過剰な不安を覚えるようになった人が多いのです。問題の本質は、この「対人関係への過剰な不安」であって、「どこに通うか」ではありません。過剰な不安のままで何らかの通所施設に通うことは、かえってその不安を強めてしまうことになりかねません。
もし、その人が、対人関係への過剰な不安によって在宅不登校や引きこもりになったとしたら、「在宅からスタートできる」ということは、選択しやすいことです。イーズで最も求められている活動は「交流」です。人と出会いたい、最初は無理でもいつかはつながりたい、そういった思いを持っているが、なかなか踏み出せないでいた、そのような人のニーズに応えたいと思っています。
また、対人関係への過剰な不安がない人には、「近くにフリースクールがない」「不登校に偏見のない人と交流したい」「ホームスクーリングを実践しながら子ども時代を有意義なものにしたい。そのためにも仲間と出会いたい」といったニーズで選ばれており、やはり社会性を大事に考えて入会する人が多いと思います。